ここでは「糖尿病食事療法のための食品交換表」を使って栄養計算をします。この食品交換表は適正なエネルギー量で、しかも、栄養のバランスのとれた食事の献立が、手軽にできるように工夫されたものです。
1単位を80kcalで計算します。なぜ1単位が80kcalかというと、日本人が食べている食品が80kcalか、その倍数になっている食品が多いためです。
「組み合わせ自由な簡単レシピ」では一日の摂取エネルギーを1,800kcalにしていますので、1,800÷80=22.5で、一日に22.5単位分を食べて良いことになり、これを6つの表に配分していきます。
食べる食品に含まれている栄養素によって6つの表と調味料に区分されます。
1単位の栄養素の含有量は次の表の通りです。(糖尿病食事療法のための食品交換表第7版引用)

表1…穀物、芋類、豆など糖質が多い食品
表2…くだもの
表3…魚介、肉、卵、チーズ、大豆などタンパク質が摂れる食品
表4…牛乳など
表5…油脂、多脂性食品
表6…野菜、海藻、きのこ、こんにゃくなどほとんどエネルギーが無い食品
調味料…みそ、砂糖、みりんなど
表2~表6に単位数を配分します。

表2…1単位
表3…4.5単位
表4…1.5単位
表5…1.5単位
表6…1.2単位
調味料…0.8単位
合計…10.5単位
残りが表1…12単位
献立の作り方
一日で3つの献立を組み合わせていただくと、一日分のタンパク質と野菜類が摂れるように献立を作っています。
1食につき表3(タンパク質)は1.5単位、表6(野菜・海藻類・きのこ類・こんにゃく)は0.4単位以上摂取できるようにしています。
※献立によって単位数に過不足がある場合がありますが、ご了承ください。
表1(穀類・いも類)が1日で12単位使えますので、3回に分けると一食に4単位使えます。
表2(くだもの)1単位と表4((牛乳など)1.5単位は、食事時のデザートや間食で取り入れていきます。
表5(油脂類)1.5単位と調味料0.8単位は、その時の料理によって使い分けます。
これで日本人の食事摂取基準に定められる栄養素の取り方にほぼ近づきます。
※1 表1のご飯・食パン・麺類の1単位の量は、別の項目に載せていますので、参考にしてください。
※2 摂取エネルギーによる表1の一日に摂る単位数をお知りになりたい方は、お尋ねくだされば、その方の表3との兼ね合いを考えながら数値を出していきます。









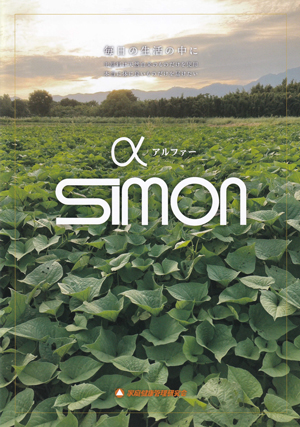


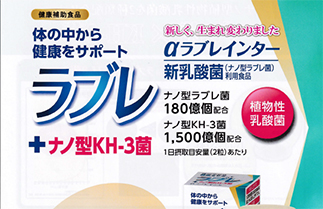


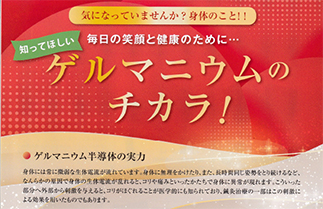





コメント